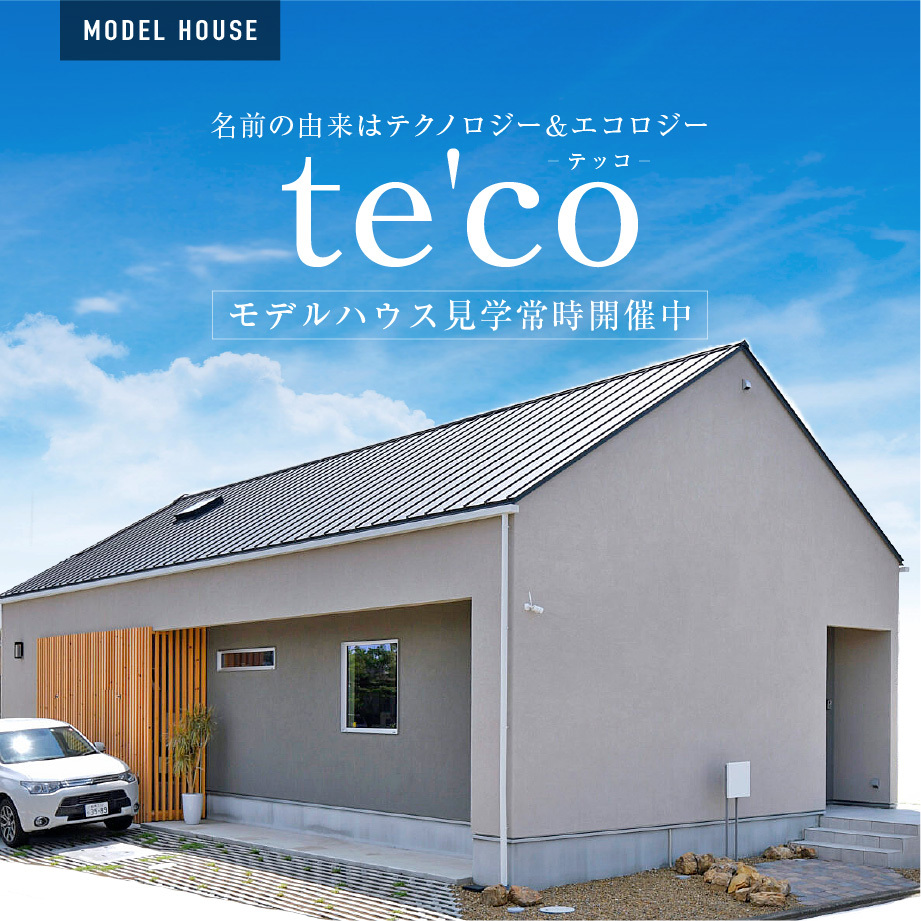長期優良住宅における「防犯等級」について
最近、闇バイトなどの横行で建物に関する防犯を意識する声が高まってきました。
実はこの防犯も、入りずらい建物になっているかを、長期優良住宅の評価によって、レベルを分類分けすることができるのです。
最近忘れていましたが、CP(防犯ガラス)などの受注が大変多くなってきています。
これは長期優良住宅の評価の一部になりますが、もし取得しなくても設計士に評価してもらい、安全な住まいづくりをすることをお勧めします!
ちなみに、長期優良住宅の認定基準において、「防犯等級」は直接的な必須要件ではありません。
1. 防犯等級とは?
防犯等級は、建物の開口部(主に窓やドア)の防犯性能を評価する基準であり、「JIS A 1510」や「防犯建物部品(CP認定)」の基準に基づいて分類されます。
防犯等級の分類(1〜3)
-
等級1:通常の施錠のみで、最低限の防犯性能
-
等級2:侵入に対する抵抗力が強く、こじ開けに時間がかかる
-
等級3:高い防犯性能を持ち、工具を使用した侵入も防ぐ
CP認定(防犯建物部品)との関係
「CP認定品」は警察庁などが推奨する防犯性能の高い建材のことで、CP認定を受けた窓やドアは防犯等級2以上に該当するものが多く、安全性が高いと評価されます。
2. 窓の防犯等級の評価例
窓の防犯性能は「破壊されにくさ」「侵入までの時間」「工具の使用有無」などによって評価されます。
| 防犯等級 | 侵入のしやすさ | 具体例 |
|---|---|---|
| 等級1 | 施錠のみ | 一般的な窓(単板ガラス・普通のクレセント錠) |
| 等級2 | 一定の耐久性 | 防犯ガラス(合わせガラス)、二重ロック付きの窓 |
| 等級3 | 高い防犯性能 | 強化ガラス+防犯フィルム+シャッターや面格子付き |
安全な窓の形とは?
-
小さめの窓(侵入しづらいサイズにする)
-
高い位置の窓(足場がないと届かない位置に設置)
-
面格子やシャッター付きの窓(外部からの侵入を物理的に防ぐ)
-
防犯合わせガラスの使用(2枚のガラスの間に強靭なフィルムが入っている)
例えば、1階のリビングの大きな窓には「防犯合わせガラス+面格子+ダブルロック」の組み合わせが推奨されます。
3. 防犯等級を定めた経緯
日本では2000年代に空き巣や侵入犯罪が増加し、その多くが「窓や玄関からの侵入」によるものだったため、建物の開口部の防犯性能を向上させるために防犯等級が定められました。
主な背景
-
1990年代〜2000年代に侵入窃盗事件が急増
-
2002年に警察庁・国土交通省・住宅メーカーが協力して「防犯建物部品(CP認定)」制度を開始
-
JIS(日本工業規格)に基づく「防犯性能の基準」が整備され、防犯等級の概念が広まる
これにより、「破壊されにくい窓・ドア」の重要性が認識され、防犯性能を示す等級が設定されました。
4. 防犯等級の審査方法
防犯等級の審査は主に以下のような方法で行われます。
① 物理的な試験(JIS A 1510規格に基づく)
-
こじ開け試験:バールなどの工具を使い、どの程度の時間で窓やドアを破壊できるかを検証。
-
破壊試験:ガラスや錠前を一定の力で叩いたり、こじ開けたりして耐久性をチェック。
-
耐貫通試験:ハンマーやドライバーを使用し、どれくらいの衝撃で穴が開くかを評価。
② CP認定試験(警察庁・国土交通省が関与)
CP認定を受けるためには、建材メーカーが防犯試験をクリアし、警察庁・国交省・建築学会などの基準を満たす必要があります。
まとめ
-
防犯等級は1〜3まであり、等級が高いほど侵入しにくい設計になっている。
-
窓の防犯対策には、防犯合わせガラス・面格子・シャッター・二重ロックなどを組み合わせるのが有効。
-
防犯等級は2000年代の侵入犯罪の増加を背景に整備され、CP認定制度と連携している。
-
審査は物理的な破壊試験や耐久性試験などを経て行われる。
住まいを設計する際には、防犯等級の高い建材を採用することで、安全性を向上させ、長期間安心して住める住宅にすることが重要です。